第二次性徴の憂鬱
トランスジェンダーの子どもたち、女性・男性という性役割がしっくりこない子どもたちにとって、身体に大きな変化がある第二次性徴の時期を乗り越えるのはとても大変です。インターネットには不正確な情報も多く、親子ともに振り回されてしまうこともあります。

トランスジェンダーの
子どもたちの経験
他の人の目が怖くて、学校に行けなくなった
自分の身体が変わっていくのが恐怖で、自分を傷つけることがあった
先生に相談したら、制服や合宿などで柔軟に対応してもらえた
制服や下着が嫌だった
インターネットの海外通販でホルモン剤を買って、自己判断で大量に飲んで体調を崩し、緊急搬送された
知っておいて欲しいこと
- 性自認(自分の性のとらえ方)は、時期によって揺らぐ子もいれば、ずっと一貫している子もいる
- 性同一性障害は精神障害の項目から外れることになった(WHOでGender Incongruence(性別不合)という項目が新設)
- 制服やトイレの相談は、診断書がなくても可能(少しの環境調整のために診断書を求めるのは、むしろ人権侵害になりうる)
- 本人が身体の状況で苦しんでいるなら、ジェンダー・クリニックに相談して、第二次性徴を一時的に止める薬を処方してもらうこともできる
- 高校、大学や企業の対応事例はどんどん増えており、トランスジェンダーであっても、進学も就職も諦めなくていい
おすすめ♥ブックス
「トランスジェンダーと職場環境ハンドブック〜だれもが働きやすい職場づくり〜」
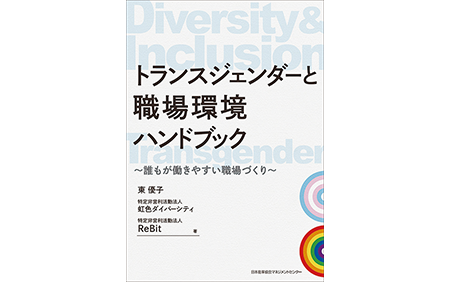
著者:東 優子、虹色ダイバーシティ、ReBit
発行:日本能率協会マネジメントセンター(2018)
「しまなみ誰そ彼」
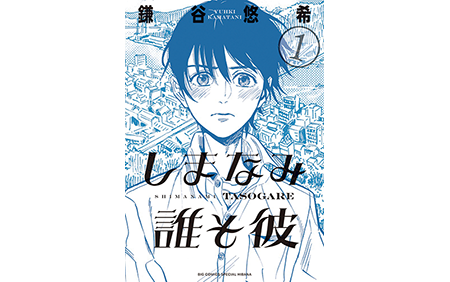
著者:鎌谷 悠希
発行:小学館(2015)